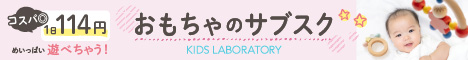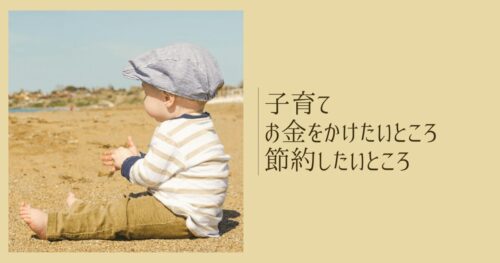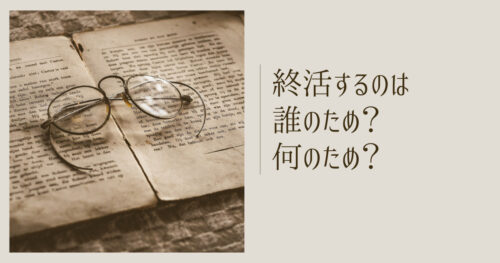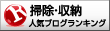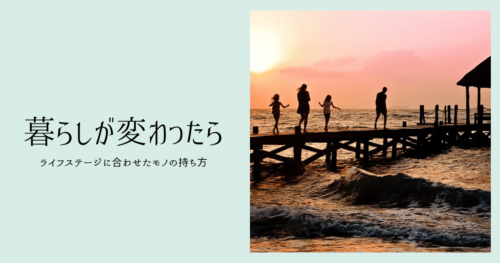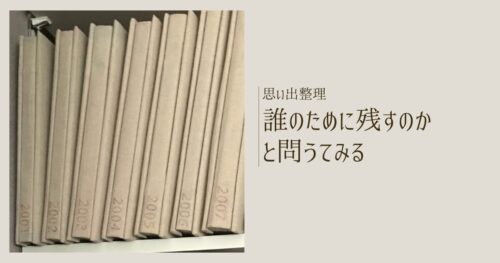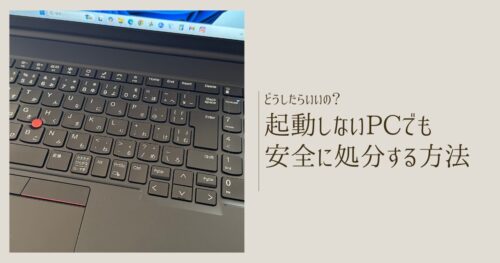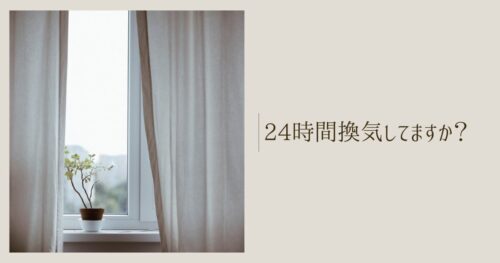悩めるる
悩めるる子供が生まれてから家の中が片付かないのよね



仕事を始めたら、家事に手が回らなくなってしまったわ



今までやってたことが、だんだん面倒になって…
こんなお悩みに答えます
ついのすみかづくり(@tsuinosumika15)
整理収納アドバイザーの akemiです
転勤で様々な家に移り住み
その都度暮らしを一から作り直してきました
ライフステージの変化を
肌身で感じながら、現在50代後半
そんな私が
楽に暮らせる空間をつくるための
「暮らしの変化」について解説します
- 暮らしとモノの関係性
- ライフステージごとに必要なモノの持ち方考え方
片付けが上手くいかず
暮らしにくくなったと感じる人の
参考になれば幸いです
ライフステージとモノの関係性
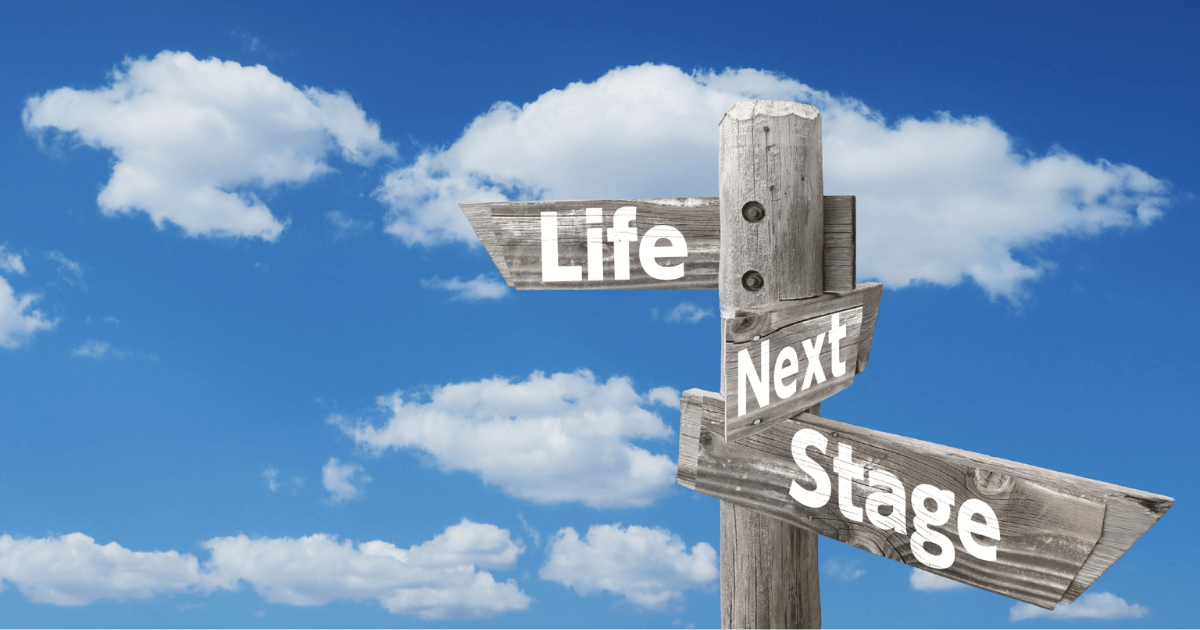
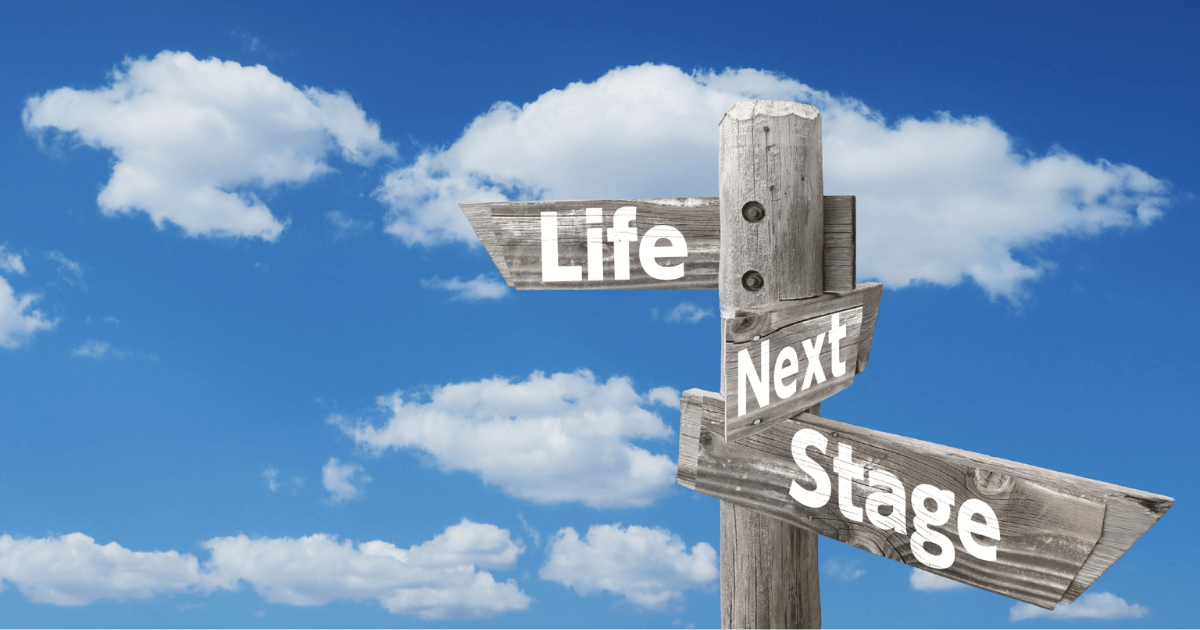
人の一生には
- 幼年期
- 青年期
- 壮年期
- 老年期
また、人生の節目では
- 独立
- 就職
- 結婚
- 出産
- 別居
- 同居
- 定年 など
といった
家族の構成や、ライフスタイルによって
暮らしの変化をむかえる段階があります
もし
- 片付かない
- 家事に手が回らない
- 面倒臭い、億劫になることが増えた
と感じていたら
これまでのモノの持ち方が
今のライフステージに合わなくなってきているのかも知れません
暮らし方が変われば
持つモノ・モノの持ち方も変わってきます
暮らしの変化に対応しないと
暮らしにくさにつながります



モノの持ち方が大きく変わるライフステージごとに、意識すべきポイントを見ていきましょう
ステージごとのモノの持ち方考え方
独立


親元を離れ、暮らしを一から始める時
これまで自分のモノだけでよかったのが
生活に必要なモノすべて準備し
管理する必要が出てきます
取り急ぎで揃えてしまうことも多いのですが
実は、上手に選べば長く使えるモノも多く
これから先の暮らしを考えた時
買い替える必要が無いモノ
頻度が少なくてすむモノもあります



わが家でも、主人が一人暮らしを始めた30年前に買ったモノで現在も使っているモノがいくつかあります
キッチン用品
- 包丁
- キッチンばさみ
- ボウル・ざる
- スプーン・フォーク など
一度買えば、なかなか買い替えないモノです
ステンレス製は高価なモノも多いですが
丈夫で長く使えます
キッチン用品のプラスチック製品は
軽く、劣化も少なく、長く使えます
とりあえず100均でと考えるよりも
こだわって選んでみてはいかがでしょうか
わが家のお墨付きご長寿キッチン用品です
▼おすすめのキッチンツールをご紹介しています


収納用品
昔から日本の家は、「基準寸法」単位モジュールをもとに建てられています
| 通称 | 一間 | 半間 | 奥行 |
| 京間 | 1910 | 955 | 880 |
| 江戸間 | 1760 | 880 | 880 |
| 団地間 | 1700 | 850 | 850 |
収納用品がシンデレラフィットするのは
モジュールに合っているからです
なので、モジュールを意識して規格設計されているモノを選べば、住まいが変わっても互換性が高くなると感じます
変わるものと変わらないもの
無印良品は2004年に「家」を販売する際に、畳というモジュールは大切にしながら、nLDKという様式に変わるものとして「一室空間」を提案しました。
無印良品が、畳というモジュールを大切にしているのには理由(わけ)があります。
畳の寸法は3尺×6尺です。1尺は約30.3cmですが、西洋の基準寸法であるフィートもほぼ同じ30.48cmです。これは偶然ではなく、いずれも人体の寸法から来ており、なるべく合理的な寸法で暮らしやすくと考える住宅のモジュールとして、非常に理にかなっているわけです。
ですから、このモジュールは変わらずずっと使えるものであり、無印良品では家に限らず、家具や生活雑貨についても、この畳モジュールを念頭にデザインされています。
引用元:「モジュール」と「様式」 | 住まいのかたち | 住まいのコラム | 住まいのかたち|Magazine for MUJI LIFE
大きな家具よりも
軽くて使いまわしのきく収納ケースが
ライフステージが変わっても長く使えます



わが家では、奥行き44.5cmのモノを高さ18cmと30cmと組み合わせて使っています
結婚


モノが二人分に増えるので
スペースに対して持てる数・量を意識することが大事です
新しく家具や家電を購入する際には
下記のポイントを意識してみて下さい
家具
一度買うとなかなか買い替えるものではなく
買い替えの際は古いモノを処分する手間も必要です
- 大きさ
- 素材
- 耐久性
- 手入れの手間
を考えて慎重に決めることをおすすめします
家電
耐用年数と呼ばれる寿命があります
個体差がありますが
わが家が結婚24年の間に買い替えた回数は
- 冷蔵庫 2回
- 洗濯機 3回
- エアコン 2回
- テレビ 3回
- オーブンレンジ 2回
- 掃除機 3回
- トースター 4回
中には機能的な買い替えもあり
使用頻度による差はありますが
大型家電に関しては
約10年前後だと考えています
多機能・高機能であればあるほど高額です
使わなければ無駄になるので
暮らしに必要な機能だけ選びましょう
出産


一番モノが増え
入れ替わりが激しい時期です
かさばるモノは、ネット通販を利用して
必要な分だけ上手に購入しましょう
使用期間が短いモノも多く
次使うのがいつになるのか分からないので
レンタルやサブスクを積極的に利用してみてはいかがでしょうか
ベビーベッドは、レンタルして一番良かったと感じるモノです
他も「レンタルで十分だったな」と
今振り返ればそう思います
わが家も、ジャングルジムやすべり台を
購入した後の処分に悩んだので
レンタルサービスはおすすめです
わが家の子育て時期には
無かったサービスですが
子供のおもちゃは
その時期その時期と興味が変わるので
「これいいな」と思いました
必要な時期に、必要なモノを
収納に悩むことなく持つことが出来ます
つい子供のモノにお金をかけてしまいがちですが、大きくなればなるほど、子供はお金がかかります
- 塾・習い事
- 進学
- 仕送り
- 成人祝い
- 国民年金支払い など
子供が小さい間にこそ、出来るだけ節約して貯めることをおすすめします



わが家は子供一人で、現在大学生ですが、びっくりするほどお金がかかってます
▼借りるメリットについて、こちらの記事で更に詳しく解説しています
▼子育てにかかるお金について解説しています
子供の独立


親の立場から見た子供の独立においても
暮らしは大きく変化します
子供が家を出た後も
住んでいた時と同じ状態のまま
というご家庭も多いのではないでしょうか
勉強机や教科書・雑誌、大量の服など
今後必要となる可能性が低いモノまで取り置いてしまうと
たまに帰ってきた時にも
くつろげる空間とは言えません
結婚や独立して
別に所帯を持っているなら尚更です
空間に余裕があり、他に用途が無くても
掃除などのメンテナンスも必要です
今後も暮らす家族にとって
有効な空間にすることを第一に考えましょう
ただし
持ち物本人の確認無しに
処分してはいけません
家族みんながモノに対して
意識が持てるようになるのが望ましいですね
親の介護


親もいつまでも若い頃のままではありません
ずっと頼りにしてきた親と
立場が逆転するのが老いです
- 病院の付き添い
- 車いす生活
- 認知症
- 寝たきり など
私自身、実・義理親で経験しています
介護のため同居するケースもよく聞きます
程度の差はあれ
おそらく誰しもにおとずれる段階です
暮らしが大きく変わるからこそ
楽に暮らせる空間を、早い段階で
作っておくことが大事だと感じます
▼将来に不安を残さないためにも、親子で話し合う機会を持つことが望まれます


定年


そう遠くない将来
わが家でも迎える段階です
長い間一生懸命働いてきたからこそ
モノの後始末に追われるのではなく
好きなことに向き合える暮らしを
送りたいですね
一方で、家事に定年はありません
炊事、洗濯、掃除は
生きている間ずっと続きます
だからこそ
それまでにモノと向き合い
本当に必要なモノだけに囲まれた暮らしを
つくることが大事だと考えています
と同時に
お金の心配をしなくてもいいように
何にどれくらい必要なのか
そのための資産をどのように準備するのか
家計についても
しっかり備えておく必要があります
▼今を安心して生きるための「終活」について解説しています
▼「ついのすみか」と呼べる家の在り方について解説しています
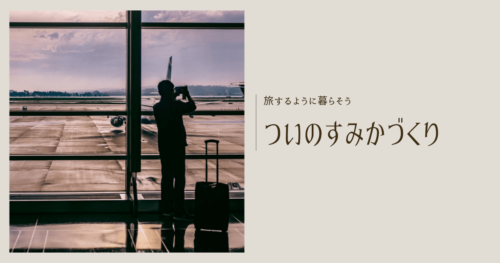
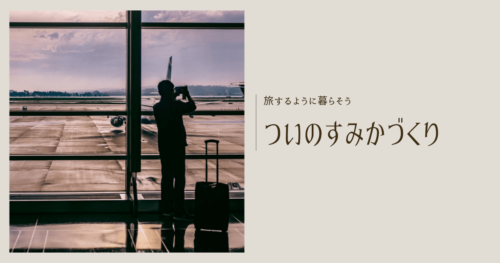
まとめ


暮らしの変化とモノの持ち方考え方
- ライフステージとモノの関係性
持つモノが今のステージに合わないと、暮らしにくいと感じる - ステージごとのモノの持ち方考え方
独立 買い替えの必要がないモノを選ぶ
結婚 スペースとモノの数・量を意識する
出産 レンタルやサブスクを積極的に利用する
子供の独立 部屋を有効活用する
親の介護 楽に暮らせる空間をつくっておく
定年 本当に必要なモノと資産を持つ
ライフステージの変化で
モノが増えて手狭になったからと
たとえ広いところに引っ越したとしても
モノの持ち方を意識しなければ
空間はあっという間に
いっぱいになってしまいます
家族もずっと一緒
というわけにはいかないので
広い家にひとりになる可能性もあります
独身や子供のいない夫婦にも
歳を重ねることで
ライフステージの変化は起こります
だからこそ
今、どのステージにあっても
今、必要なモノを意識して持つことが
大事なのではないかと感じます